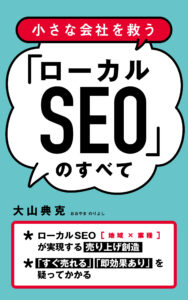AI時代に求められる導入事例の力
近年、生成AIの進化により、コンテンツ制作の在り方が大きく変わりつつあります。特にBtoB企業では、Webメディアやオウンドメディアを活用した情報発信が欠かせません。その中でも「導入事例」は、製品やサービスを実際に導入した企業の声を通じて具体的なメリットを伝える重要なコンテンツです。AI時代において、企業はこのような一次情報をどのように活用すべきでしょうか?
AIが書ける記事、書けない記事
AIの進化により、事実を整理した記事や定型フォーマットの記事はほぼ自動で生成可能になりました。例えば、特定トピックの解説記事、データに基づくレポート、ニュースの要約などがその代表例です。SEO記事もAIの得意分野であり、キーワードを適切に配置し、競合記事を参考にしたコンテンツの作成が容易になっています。実際、そのような記事はすでに大量生産されているように思います。
しかし、AIには限界があります。それは「一次情報を持っていない」ことです。AIは既存のデータや公開情報をもとにコンテンツを生成するため、企業独自の事例、専門家の知見、業界のリアルな動向、ユーザーの声など、現場に即した情報を生み出すことはできません。これらの一次情報を入手するには、人間による取材や分析が不可欠です。
BtoBコンテンツにおいては、一次情報の有無が差別化につながります。AIに書かせただけの他と同じような記事では、競合企業のコンテンツと差別化はできません。AIは効率的なデータ整理や一般的なトピックの解説には有用ですが、企業独自の視点や現場のリアルな知見を反映した価値あるコンテンツを生み出すには、人間の介在が必要です。
BtoB企業が真の差別化を図るには、AIでは作れない一次情報を活用することが不可欠です。その代表例が「導入事例記事」です。実際の顧客の声や、現場での成功体験、具体的な課題解決のプロセスなど、独自の価値を持つ情報を記事にして発信することで、効果的な差別化が可能になります。

BtoB企業における導入事例の重要性
「導入事例」は、自社の製品やサービスを実際に導入した企業の実例を紹介するコンテンツです。「成約事例」「ユーザーインタビュー」などとも呼ばれ、実際の顧客の声を通じて製品・サービスの価値を伝えることができます。BtoB企業にとって、導入事例は単なるプロモーションツールではなく、信頼性の向上や差別化のための重要な資産となります。
信頼性の高い情報で購買プロセスを後押し
BtoBビジネスでは、BtoCと異なり購買プロセスが長く、複数の意思決定者が関与します。そして導入前には慎重な比較検討が行われるため、信頼できる情報が必要不可欠です。
製品のWebサイトやパンフレットでは、製品やサービスのメリットを一方的に伝えがちであり、見込み顧客は「本当に効果があるのか?」と疑問を持つことがあります。一方、導入事例では、実際に課題を抱えていた企業がどのように製品・サービスを活用し、どのような成果を得たのかを具体的に示せるため、説得力が増します。
また、導入を検討している企業にとって、社内稟議を通す際の資料として活用しやすい点もメリットです。具体的な成功事例を提示することで、社内の意思決定をスムーズに進めることができます。
差別化要素として有益なコンテンツ
導入事例は製品・サービスの強みを具体的に示し、競合との差別化を図る上で有効な手段です。特に以下の点で大きな価値を持ちます。
- 具体的なユースケースの提示
抽象的な機能説明では伝わりにくい活用シーンや業務改善のプロセスを、具体的な事例を通じて可視化できます。これにより、見込み顧客は「自社でも同じように活用できる」というイメージを持ちやすくなります。 - 営業ツールとしての活用
商談時に導入事例を提示することで、顧客の共感を得やすくなり、意思決定を促進します。特に同業他社の成功事例は説得力が高く、営業の現場で強力な武器となります。 - マーケティング施策での活用
導入事例をWebサイトに掲載すれば、SEO効果が期待でき、問い合わせの増加につながります。また、ホワイトペーパーやメールマーケティングのコンテンツとして活用することで、見込み顧客の関心を引き、リードの育成を促進できます。
ブランド価値向上に
導入事例の発信は、自社のブランド価値を高め、市場でのポジショニングを強化する上で有効です。
- 信頼性の向上
業界をリードする大手企業や公的機関への導入実績を示すことで、製品・サービスの信頼性が向上します。特に、厳格な審査基準を持つ企業や官公庁、医療機関などでの採用実績は、品質や安全性、サポート体制の充実度を証明する材料となります。 - 市場での認知拡大
多様な業界での導入事例を持つことで、製品の汎用性や応用可能性を示すことができます。これにより、新規顧客の獲得につながり、業界内でのプレゼンスを確立できます。
また、導入事例の蓄積は企業の実績として評価され、信頼性の高い企業として認知されるようになります。これにより、新たなビジネス機会の創出にもつながるのです。
既存顧客との関係強化に効果
導入事例の制作は、単にコンテンツを作るだけでなく、顧客との関係強化にもつながります。
- 顧客企業のPR効果
事例に登場する企業は、IT製品なら「DXを推進する先進企業」、製造業なら「業務効率化を実現した企業」として、業界内での評価が高まります。導入事例の公開は、顧客にとってもブランディングの機会となるのです。 - 顧客の声を直接フィードバック
取材の際には、営業担当者や広報担当者だけでなく、開発担当者やカスタマーサクセス担当者が同席するケースもあります。これにより、顧客の生の声を聞き、製品・サービスの改善に活かすことができます。
このように導入事例は、コンテンツとしての価値だけでなく、営業、マーケティング、ブランド戦略、顧客関係強化といった多方面での効果をもたらします。BtoB企業が競争力を高めるためには、AIでは作れない一次情報を活用した導入事例コンテンツの発信が重要になるのです。
販促だけでない、導入事例の使い道
「導入事例」という手法は、販促資料として使ったり、ブログやオウンドメディアに掲載したりするだけでなく、さまざまなマーケティングチャネルで活用できる有用なコンテンツです。
Webメディア広告や雑誌広告としての活用
Webメディアや雑誌の広告記事として、導入事例を展開することも有益です。単に、製品担当者にインタビューして製品を宣伝するよりも、実際の活用事例や成果を示すことで読者の関心を引きやすく、より深い理解を促すことが可能になります。特に課題解決のプロセスや具体的な数値を含めることで、読者自身の状況に置き換えて考えやすくなり、広告としての説得力が高まります。
導入した顧客が大手企業や上場企業の場合、そのネームバリューを借りられるという意味合いも大きいですね。「○○社が採用した手法とは?」といった見出しは、読者の興味を引き、広告の閲覧数を大幅に伸ばすことにつながるでしょう。
広報媒体での活用
CSR報告書や統合報告書、株主報告書、会社案内などの広報媒体においても、導入事例は使えます。「お客さまの声」「取引先の声」として導入事例を掲載することで、企業の事業価値や社会的価値をより具体的に示せます。例えばCSR報告書では、「当社製品を活用してCO2削減を達成した○○社」といったかたちで事例を紹介するのもいいでしょう。
社内向けコンテンツでの活用
社内イントラネットやニュースレターなどで導入事例コンテンツを活用するのもおすすめです。例えば大企業では、各部署の機能や取り組みを全社員が把握することは容易ではありません。そこで、社内イントラネットやニュースレターなどで導入事例を共有することで、部署間の連携促進や業務効率の向上につながります。
私(平)が実際に担当した案件では、新設されたデジタルチームの成功事例を社内向けに発信するコンテンツを制作しました。特定の部署の売上向上に貢献した施策と成果を具体的に紹介することで、他部署からの問い合わせや協業依頼の増加を図るという目的がありました。
また社内報においても、導入事例コンテンツは魅力ある企画の一つとなります。社員に読んでもらうことで、ベストプラクティスの水平展開や、部署を超えたナレッジ共有の促進につながります。
導入事例制作をライターに依頼するメリット
さて、導入事例記事を作成するには、担当者(多くは販促担当者、広報担当者)が作る方法と、外部の制作会社、外部のライターに依頼する方法があります。ライターに依頼するメリットは何でしょうか。
高品質な原稿をサポート
導入事例の取材では、製品・サービスの価値を引き出しながら、導入の背景、課題、解決プロセス、そして成果創出に至るまで、顧客のエピソードを引き出す必要があります。経験を積んだライターは、これらの要素を効果的な流れで構成し、読み手の心に響く記事に仕上げていきます。特に、複数の関係者(顧客、製品提供企業だけでなく、代理店など)が関わる導入事例では、それぞれの視点をバランスよく配置することで、より説得力のある内容になります。
業務効率の向上
企業の広報担当者や販促担当者が記事を作成することも可能ですが、取材から記事作成、図版の準備までを一貫して行う必要があり、慣れない担当者にとっては大きな負担です。生成AIを活用したとしても、精度の限られた文字起こしや、記事の一部分の作成を効率化できるくらいでしょう。納得できるコンテンツに仕上げるには、やはり人の手が必要です。
原稿作成をライターに依頼すれば、企業の担当者は記事作成にかかる時間を削減できます。その分、本来の業務である戦略立案やプロモーション施策の企画・実行に集中でき、より効果的なマーケティング活動を展開できます。
客観的な視点での編集・構成
社内の担当者は、自社の製品やサービスについて詳しく知っているだけに、「当たり前」と思って説明を省略してしまったり、専門用語を多用したりする傾向があります。一方、外部ライターは第三者の視点で取材内容を整理し、読み手にとって分かりやすい表現や構成で記事を作成できます。また、他社事例の執筆経験を活かして、より効果的な切り口や表現方法を提案することも可能です。これにより、より多くの見込み顧客に響く導入事例を制作できます。
取材を成功に導くためのポイント
導入事例の制作をどのように進めるべきか、考えてみます。
事前準備が成功のカギ
導入事例の取材を成功させるためには、入念な事前準備が欠かせません。まず、営業担当から顧客情報や導入背景といった情報を入手し、全体像を把握します。そしてインタビュー項目を作成し、顧客企業に事前共有します。撮影が必要な場合は、必要なカットについて事前に確認を取っておくことが重要です。
取材では効果的な質問の流れをつくる
取材では、一定の流れに沿って話を進めていくことが効果的です。最初に顧客企業が抱えていた課題について詳しく聞き、そこから製品・サービス導入の決め手となったポイントへと展開していきます。続いて具体的な導入プロセスを確認し、実際にどのような効果や成果が得られたのかを掘り下げます。最後に今後の展望や期待を伺うことで、ストーリー性のある内容に仕上げられます。
具体的なエピソードを引き出す
インタビューを深めるコツは、具体的なエピソードを引き出すことです。「具体的には?」「例えば?」といった質問を重ねることで、読者の心に響くリアルな声を集められます。また、可能な限り数値化できる効果を確認することも重要です。「前年比でどれくらい改善しましたか?」といった質問により、説得力のあるデータを得られます。
担当者との連携で内容を充実させる
取材の際は、製品・サービスについて深い理解がある担当者も同席することをおおすすめします。ライターが中心となって進行しながらも、担当者ならではの視点で補足質問を加えることで、より充実した内容になります。
ビジュアル面の工夫
写真や画像は導入事例記事に説得力を持たせる重要な要素です。製品・サービスの利用シーン、インタビュー対応者の表情やしぐさ、オフィス環境など、顧客企業の承諾を得た上で必要な場面を撮影します。プロのカメラマンを起用するのが理想的ですが、コスト面を考慮する場合は、ライターや担当者が撮影を担当することも可能です。
時間管理のコツ
時間配分については、インタビュー本編で1~1.5時間を目安とし、撮影の時間も考慮した全体スケジュールを組むことが大切です。取材開始時に全体の流れを説明し、限られた時間を効率的に使うよう心がけましょう。
このような綿密な準備と段取りを行うことで、質の高い導入事例記事を制作できます。他にも細かいポイントはいろいろありますが、長くなりますのでこの程度にしておきましょう。
まとめ:AI時代だからこそ「導入事例記事」に価値がある
生成AIの進化により、解説記事やSEO記事の価値は相対的に低下する一方、一次情報を活用した導入事例記事の重要性は高まっています。BtoB企業が競争力を強化するためには、取材を通じた独自の導入事例記事の作成が不可欠です。
なお当社では、IT製品をはじめBtoB分野の導入事例(成約事例)記事を多く手掛けてきました。以下はその一例です。
- クラウド型ファイル送受信サービスの導入事例
- オンライン校正用サービスの導入事例
- 法人クレジットカードの導入事例
- M&Aマッチングサイトの成約事例
- 営業支援システムの導入事例
- グループウェアの導入事例
- ビジネスインテリジェンス(BI)システムの導入事例
- データアーカイブ(磁気テープ)ソリューションの導入事例
- ストレージ製品の導入事例
- RPAソフトウェアの導入事例
- エンドポイントセキュリティソリューションの導入事例
- クラウド型シフト管理サービスの導入事例
- 薬剤師向け監査業務支援システムの導入事例
- 印刷機の導入事例
- ノーカーボン紙の導入事例
自社の製品・サービスの導入事例をコンテンツとして発信したいとお考えなら、ぜひご相談ください。取材を通じて、AIでは作れない高品質な記事を提供いたします。